※この話は実話を基にしたリアルな物語ですが、実在する団体や個人名を伏せるために、至る所に仮名を使っています。
神奈川県Y市でのホテル暮らし
少年Aはヤクザとのトラブルや抗争をきっかけに地元を離れ、神奈川県Y市のラブホテルに部屋を借りて暮らしていた。
ラブホテルに部屋を借りて暮らすってどういう事?と思われたかたもいらっしゃるかと思いますが、当時少年Aの周りでは割と同じような生活をしている人間がいて、要するに同じ部屋に長期ステイするだけで、特段住居契約を結ぶとかそういうわけではない。
ドヤ街なんかの簡易宿泊所よりは快適に暮らせて、出かけている間に清掃やベッドメイクもしてくれるんで住みやすいんです。
ラブホテルなので異性を連れ込んでもなにも問題ないですし、ビジネスホテルよりも不良少年や不良少女は当時ラブホテルに居着いていたのです。
少年Aはこの時、付き合っている女性がおり、その女性も一緒にラブホテルの同じ部屋に暮らしていた。
そのラブホテルでの暮らしはすこし独特で、少年Aとその彼女が201号室、となりの202号室には少年Aの彼女の実姉と、仕事仲間の女の子が住んでいたのである。
たいていこのホテル周辺でいるときはこの4人で行動していて、少年Aは小ハーレム状態であった。
ちなみに少年Aの彼女、その実姉、その友人の女は全員高級デリヘル嬢を生業にしており、要するに風俗嬢従事者である。少年Aは元々裏社会や夜の世界の住人なので、そういう出会いも多かったのだ。
彼女たちは仕事が終わりラブホテルに帰ってくると、フロントに「ただいま」と言って部屋に戻り、まるで自分の家かのようにくつろいだ。
たまにお互いの部屋を行き来しては、物の貸し借りをしたり、4人で朝まで遊んだりして過ごした。
あまりに暇でやる事がないときは、ラブホテルの非常用の外階段(施設の内側なので外部からは見えない中庭のような場所に通じていた)に出て、空を見上げたり1階部分の無機質な床を見つめたりして過ごした。
彼女らは昼頃、もしくは夕方頃まで眠っており、日が暮れる頃になると出勤準備をし、気分が乗らない日は仕事を休んで遊びにでかけた。
少年AはY市でまた悪い仲間を作り、昼夜問わずフラフラと街に繰り出しては不毛な時間を過ごした。
しかし彼ら彼女らは好きでこんな生活をしているわけではない。いつかこの怠惰な生活には終わりが来る事はうすうすわかっていたし、出来れば普通に働いて、普通に家族を作り、普通の生活をして穏やかに暮らしていきたいと願っていたのだ。
だが彼ら彼女らにはその普通こそが最もほど遠い。むしろ対極に位置する場所に思えた。
なぜなら生まれながらにしてその普通とは程遠い環境で育ってきたため、その普通に暮らす方法がわからないのである。
彼女ら3人には家もなければ住所もない。家族も頼る人間も場所もない。
幼い頃から施設で育ち、親の愛情や普通の家族の暮らしという物をまったく知らないのだ。
施設での暮らしを知らない人間からすると想像しがたいかもしれないが、多感な時期に不安定な環境で過ごす子たちの多くはすさみ、そしてグレてゆく。
施設内での暴力やトラブルも絶えないし、自殺する人間も少なくないのだ。
少年Aの父親はアルコール依存症で、仕事が休みの日には早朝から夜中まで飲み続け、家の中で暴れた。
母親は逆に人格者であり、その奇妙なバランスが非常にストレスだった。
11人家族という大人数の中で育ち、その多くは非常に癖があり特殊だったため、一般の家庭で育った人間とのズレに苦しんだ。
親戚関係にも裏社会の人間が多く、身内でのトラブルも絶えなかった。
生まれ育った街も俗に言う日本のスラム街というやつで、小学生のうちからナイフを持ち非行を繰り返す者もいたし、中学生になると先輩からの熾烈なヤキ、リンチ、カンパなどもあった。
周りの大人たちも犯罪者が多く、アルコール、ドラッグ、盗み、暴力、人の死などがとても身近で、そういう物に対しての感覚が麻痺したまま育ったのである。
実際この文章を執筆している今まで、何人もの知人友人が命を落とし、行方不明になっている。
こんな環境で育ってきた人間が普通を求めても、なかなかに難易度が高く、何から始めて何をすれば良いのかもさっぱりわからないのである。
少年Aと彼女の実姉は薬物を常用しており、たまにその影響下で非常用階段に出ると、見上げた空に昇っていき世界と調和できるような感覚になり泣いた。
シラフでも階段から地上を見下ろしていると、「このまま飛んで死ねば、来世では普通に穏やかに暮らせるかも…」なんて中二病チックな考えが浮かぶ事もあった。
彼ら彼女らも、自分たちなりに足りない頭でもがいているのだ。頭も足りないし、考えるゆとりもあまりないくらいに毎日色々なトラブルが起こるので、結局良い考えも浮かばないままに歳をとり、気が付いたら取り返しのつかない所まで来てしまっている人間がほとんどなのだ。
少年Aの彼女「…なに?泣いてんの?」
少年A「ピザ…、とろうか。」
彼女の姉と友達「やりい。エビね。耳がサクサクのやつ。」



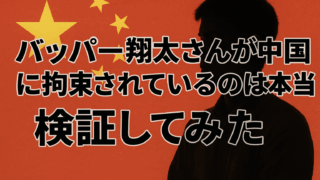





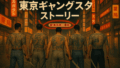

コメント